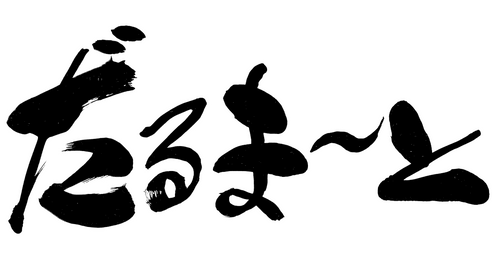だるまが赤い由来とは?赤に込められた意味まで詳しく解説

だるまと言えば『赤』と多くの方がイメージすると思います。
最近では赤以外のカラフルなだるまも人気ですが、やはり昔からの定番は赤です。
だるまが赤い理由はだるまの歴史に深く関係しているので、この記事で紹介していきます。
だるまが赤い由来は達磨大師がまとっていた衣の色
だるまの『赤』は達磨大師がまとってた法衣の『緋色』を表しています。
もとは達磨大師が緋色の法衣をまとい、坐禅をしている姿がだるま(赤)の起源です。
よって、だるまの色は『赤』ではなく『緋色』とも言えます。

達磨大師がまとっていた赤(緋色)の法衣とは
法衣(ほうい・ほうえ)とは僧侶が身につけている衣装のひとつです。
法衣の起源はインドの僧侶がまとっていた衣装で、使わなくなった布を縫い合わせたものでした。
達磨大師は南天竺(現在のインド南部)で生まれ中国に渡った僧侶ですので、上のイラストのような昔の法衣をまとっていたのだと思います。
法衣は中国や日本に伝わった後、下のイラストのような皆さんも見たことがある装飾的なスタイルになっていきました。

法衣と袈裟(けさ)は同じ意味で使われることもありますが、基本的には下にまとっているのが法衣、法衣の上に着けているのが袈裟です。
ちなみに、高崎だるまのお腹に描かれている金色の縦模様は袈裟を表しています。
法衣は色によって位階が分かれます。
時代や宗派によって色と位階の組み合わせは異なりますが、仏教の中で『緋色』は最上位に位置しています。
禅宗の開祖である達磨大師は位の高い僧侶だったので、緋色の法衣をまっとっていたのだと考えられます。
赤が持つ力は伝染病からも人々を守った?
江戸時代に疱瘡(ほうそう、別名:天然痘)という病気が大流行していました。
疱瘡は伝染力が強い上に死亡率が高く、後遺症として顔にひどい痕が残ったり、失明の可能性もある病気です。
当時の疱瘡は不治の病で、疱瘡神の仕業と信じられるほど、人々に恐れられていました。
疱瘡神は火や血の色である赤を嫌うと言い伝えがあり、患者や子供の周りには赤い玩具や絵を置き、疱瘡除けとしていたようです。
その風習から赤いだるまや赤で描かれた達磨大師の絵は江戸の人々から重宝されていました。
疱瘡は1980年にWHOが根絶宣言をしましたが、今も名残として日本にはだるまを始めとした赤い玩具があるのです。
だるまの他に今も尚残る赤い玩具
赤べこ

会津(福島)の郷土玩具。「べこ」は会津弁で「牛」の意味。
魔除け、疫病除けなどのパワーがあると言われています。
さるぼぼ

飛騨高山(岐阜)のお土産として有名な人形。「さるぼぼ」は飛騨弁で「猿の赤ん坊」という意味。
安産、良縁、子供の成長、無病息災などのなどのパワーがあると言われています。
まとめ
だるまが赤い由来は達磨大師が緋色の法衣をまとっていたからです。
緋色の法衣は仏教では最上位に位置し、達磨大師の位の高さがうかがえます。
また、赤の色には疱瘡から身を守る力があると信じられていて、だるまを始めとした赤い玩具は今でも数多く日本に残っています。